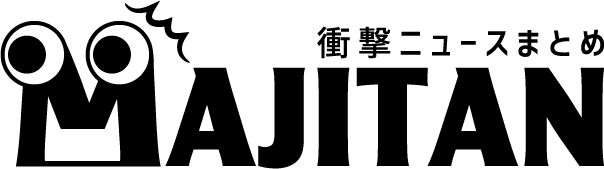とらや羊羹の批判が大炎上、ネットユーザーが一斉擁護
とらや羊羹の批判が大炎上、ネットユーザーが一斉擁護
概要
2025年8月20日、ベルギー在住の日本人駐在員の妻が、夫の取引先から贈られた老舗和菓子店「とらや」の羊羹についてSNS「X」に投稿し、「海外駐在員に喜ばれないお土産」と厳しく批判した。この発言は瞬く間に拡散し、多数のユーザーから羊羹の伝統的価値や保存性を擁護する声が寄せられ、大炎上に発展。投稿は削除されたが、和菓子の文化的地位や日本土産のあり方をめぐる議論が再燃する結果となった。
背景と経緯
「とらや」は室町時代後期創業とされる老舗和菓子店で、特に羊羹は同社を代表する商品であり、国内外で長く愛されてきた。皇室御用達としても知られ、格式と信頼性を兼ね備えた和菓子ブランドの象徴でもある。羊羹は小豆や砂糖、寒天を用い、真空包装や個包装によって日持ちも長く、贈答品として非常に安定した需要を持つ。実際、外務省職員や駐在員、商社マンの間でも「日本らしい土産」としてしばしば選ばれる(朝日新聞2024年12月特集)。
一方で、海外駐在員やその家族にとって、日本からの土産物は生活圏や嗜好に馴染むかどうかが重要なポイントとなる。チョコレートや洋菓子など現地で容易に消費できるものが歓迎される一方、伝統和菓子のように馴染みのない味覚やカットの必要がある食品は敬遠されがちという声もある(NHK国際部2023年調査)。そのような中、今回の駐在員妻の批判は「保存や消費に不便」という生活者の視点に基づくものであった。
しかし彼女の投稿は、X上で「日本の伝統文化を軽視している」「羊羹の価値を理解していない」と炎上を招いた。とらやの羊羹は、保存性の高さや持ち運びの容易さから、むしろ「海外向けに適した土産」と考える人も多く、その点で意見が真っ向から対立した形となった。
環境的・社会的懸念 / 影響
今回の炎上は単なるSNSトラブルに留まらず、いくつかの大きな社会的含意を含んでいる。
まず一つ目は、伝統文化と現代生活様式のギャップである。羊羹は長い歴史を誇る日本菓子であり、保存性も科学的に優れている。しかし受け取る側が「食べ慣れていない」「切るのが面倒」と感じれば、伝統の価値は伝わらない。この文化的摩擦は、日本から海外への贈答のあり方に再考を迫る。
二つ目は、SNS時代の発言拡散力である。個人の不満が一瞬で炎上し、伝統企業の名を巻き込む事態は以前からあったが、今回は「駐在員妻」という立場が象徴的に捉えられ、日本人社会内部での土産文化や価値観の断絶を浮き彫りにした。特にX上では、匿名ユーザーが「駐在妻バッシング」の文脈と結びつけ、社会的ジェンダー論争にも発展している。
三つ目は、土産文化の持続可能性である。羊羹は紙や木箱を用いた包装が多く、環境負荷や輸送効率の議論とも無関係ではない。駐在員や海外赴任者は、航空便の重量制限や荷物管理に敏感であり、「軽量・簡便・食べやすい土産」へのニーズが高まっている。その点で、羊羹の伝統的包装が「不便」と映る現代的感覚にも一定の合理性がある。
課題とジレンマ
この炎上が示した最大のジレンマは、「伝統と利便性の両立」にある。とらやの羊羹は日本文化を体現する象徴的商品だが、必ずしも海外生活者にとって快適な贈答品とは限らない。和菓子の重厚な価値を守りながら、現代的な利便性を備えた新しい土産の形が求められている。
また、SNS時代におけるブランドリスク管理も課題だ。老舗といえども、個人の感想が数時間で国際的議論に発展する現実に直面しており、企業は文化的価値をどう説明し、どう発信するかを戦略的に考える必要がある。
さらに、駐在員社会特有の背景も存在する。駐在員妻の生活はしばしば「優雅」と揶揄されるが、実際には現地文化や日本からの期待の狭間で葛藤することも多い。そのフラストレーションが、今回のように文化財産への批判となって噴出する場合もある。この点では、単なる「駐在妻の失言」以上に、社会的な溝が浮き彫りになっている。
私の感想と考え
今回の炎上は、和菓子の伝統的価値を再確認させる契機になったと同時に、日本人の「お土産文化」の課題を照らし出した事件であると考える。羊羹は決して「不便」な菓子ではなく、むしろ常温保存が可能で長持ちする点で優れた食品である。しかし、切り分けが必要であり、日常的に洋菓子文化に慣れた人には「ハードルが高い」と感じられるのも事実だ。
私の立場からは、和菓子業界は「伝統の守り手」としての誇りを堅持しつつも、グローバルな消費環境に対応する柔軟性を持つべきだと思う。例えば、一口サイズで個包装された「羊羹スティック」や、チョコレート風味を融合させた洋菓子寄りのアレンジ版はすでに存在する。こうした現代的商品群を強化すれば、「羊羹=古臭い・不便」という印象を和らげられるだろう。
同時に、消費者側も「文化的背景を理解する姿勢」が不可欠である。伝統食を単に「便利・不便」で切り捨ててしまうと、文化の継承や多様性が失われるリスクがある。とらや羊羹を巡る炎上は、単なるお菓子論争ではなく、日本文化とグローバル化の接点をどう設計するかという問いそのものだと感じる。
今後は、和菓子が「文化財産」と「実用品」の両立を果たしつつ、多様なライフスタイルに溶け込む形で進化していくことを期待する。
引用元
-
朝日新聞「和菓子文化と贈答品の未来」2024年12月特集
-
NHK国際部「海外駐在員と日本の土産事情」2023年調査報道
-
とらや公式サイト(toraya-group.co.jp)
-
SNS「X」上での議論ログ(2025年8月20日)