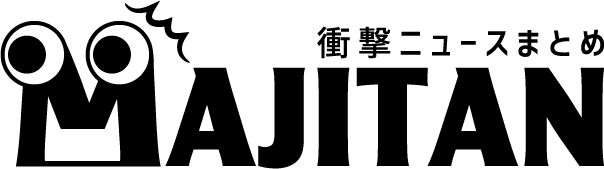日銀推計:60兆円タンス預金が日本経済を停滞
日銀推計:60兆円タンス預金が日本経済を停滞
概要
日本銀行が最新の推計を発表し、国内の「タンス預金」が約60兆円規模に達していることが明らかになった。これは低金利政策の長期化によって現金を手元に置く傾向が強まり、銀行預金や投資に資金が回らず、経済全体の停滞要因となっている。紙幣発行残高の半分近くが実際には取引に使われておらず、非取引需要として滞留していることが新紙幣発行のタイミングで公表され、消費や投資の抑制が浮き彫りになった。政府と日銀には資金循環を促す政策転換が求められている。
背景と経緯
日本における「タンス預金」の問題は、長期的な低金利政策と深く結びついている。バブル崩壊後から続くデフレ環境の中で、預金金利はほぼゼロ水準に張り付いたまま推移してきた。特に2016年のマイナス金利政策導入以降、銀行に預けても利息がつかないどころか、将来的な手数料負担への懸念が強まったことで、個人や一部の法人が現金を手元に置く動きが加速した。
日銀の調査によれば、現在発行されている紙幣残高のうち、およそ半分近くが流通に回らず、家庭や企業の金庫に眠っている。これは「取引需要」ではなく、「価値保存のための非取引需要」とされる。2024年から進められている新紙幣発行の議論の中で、こうした現金の滞留状況が改めて注目を浴びることになった。
過去にも日本では、景気後退期に「タンス預金」が増える傾向が指摘されてきた。たとえば2008年のリーマンショック後には不安心理が高まり、現金保有が急増した。今回の約60兆円という水準は過去最大規模であり、経済活動に資金が回らない状況を象徴するものといえる。
環境的・社会的懸念 / 影響
タンス預金の拡大は、日本経済の循環に大きな歪みをもたらしている。第一に、資金が銀行に預けられなければ、金融機関が企業や個人に対して融資できる資金量が相対的に減少する。これは企業の投資意欲や新規事業の育成を妨げ、長期的な成長力を削ぐ要因となる。
第二に、消費への影響も無視できない。現金を保有する人々は将来への不安から支出を抑制する傾向が強い。高齢化社会が進む日本において、医療費や介護費など将来の支出リスクを考えれば、生活防衛的な現金保有は理解できる。しかし、社会全体で消費が抑制されると需要不足が続き、デフレ圧力が再び強まる可能性がある。
さらに、防犯や社会的リスクも存在する。自宅に多額の現金を保管することで、盗難被害のリスクが高まるほか、特殊詐欺などの犯罪グループが現金保有者を狙う事例も後を絶たない。金融リテラシーの不足やキャッシュレス化の遅れが、こうしたリスクを助長している。
課題とジレンマ
政策的にタンス預金を減らすことは容易ではない。預金金利を引き上げれば銀行預金への誘導は可能だが、現在の経済状況では金利引き上げが景気を冷やすリスクが大きい。インフレ率が十分に高まっていない中での利上げは、むしろ消費や投資を萎縮させる恐れがある。
一方で、キャッシュレス決済の普及はタンス預金削減の有効策とされるが、高齢層を中心に現金信仰が根強く、完全な移行には時間を要する。政府が進めるマイナカードやデジタル給与払いの普及も、セキュリティ不安や利便性の問題から抵抗感を持つ人が多い。
さらに、国民の不安心理という要因も大きい。年金制度への信頼低下、将来の増税リスク、地政学的リスクなどが複合的に作用し、現金を「最後の安全資産」として確保する行動につながっている。政策的には消費や投資に資金を回してほしいが、国民の心理的防衛本能を否定することは難しいというジレンマがある。
私の感想と考え
私は、この60兆円というタンス預金の存在は、日本経済の停滞を象徴する非常に深刻な問題だと考える。金融政策が長年にわたり国民の信頼を十分に得られず、資金が経済循環に回らない状況を生んでいることは、日本の競争力を削ぎ続ける危険な兆候である。
まず、政府と日銀は「国民がなぜ現金を手元に置くのか」という根本原因に向き合うべきだ。年金制度の将来不安や増税への警戒心、さらには国際情勢への不安など、背景にある心理的要因を解決しない限り、どれだけキャッシュレスや金融商品を推奨しても資金は動かない。
次に、金融リテラシー教育の重要性を強調したい。現金保有だけでは資産が目減りするインフレ環境において、投資や長期的な資産形成の知識を広く共有することが不可欠だ。欧米では一般家庭が資産運用を通じて資本市場を支えているが、日本は依然として現金依存度が高い。この差が国力の差につながりかねない。
さらに、政策面では「安心してお金を使える環境」を整えることが必要だ。医療や年金制度を安定化させ、将来の生活に対する不安を軽減することこそが、タンス預金を消費や投資に転換するための鍵になる。単なる制度設計ではなく、国民が実感できる形での改革が求められている。
結論として、タンス預金問題は単なる金融の課題ではなく、日本社会全体の構造的問題を映す鏡だと私は思う。安全資産としての現金に頼る文化から脱却し、未来に投資できる社会に変わらなければ、日本経済の持続的な成長は難しいだろう。
引用元
-
日本銀行「現金流通に関する調査」2025年8月発表
-
朝日新聞 2025年8月報道
-
日本経済新聞 2025年8月特集