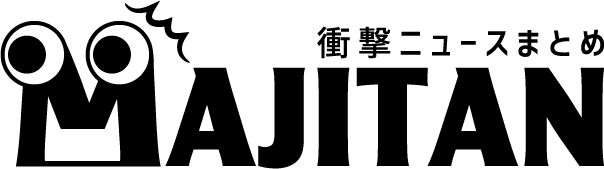日本、トルコ製攻撃ドローン導入を検討-防衛強化へ協議加速
日本、トルコ製攻撃ドローン導入を検討-防衛強化へ協議加速
概要
2025年8月19日、中谷元防衛相がトルコを訪問し、防衛産業分野における協力強化を目的に、同国製攻撃型ドローン「TB2(Bayraktar TB2)」の導入を検討する意向を示しました。2027年度までに「沿岸防衛構想」の構築を目指し、ウクライナでの実戦投入実績を参考に、比較評価および導入可否の協議を日トルコ間で進めています。また、イスラエル製Heron‑2ドローンとの併用検討の動きも報じられています。社会では、性能や法制度面、さらには防衛装備の海外依存に関する懸念が広がっており、日本の防衛政策転換点として注目されています。
背景と検討の経緯
日本がドローン戦力を模索する直接のきっかけの一つは、ウクライナにおいてTB2が実戦で高い効果を上げてきたことです。複数の報道では、この性能が日本を含む複数国の注目を集めていると指摘されています フォーブス+12EURASIAN TIMES+12caliber.az+12。
中谷防衛相は、NATO加盟国のトルコとの防衛装備協力を初めて公式表明する形で、Baykar社のドローン製造施設やトルコ航空宇宙産業(TAI)を視察しました EURASIAN TIMES+3Daily Sabah+3ウィキペディア+3。
また、2026年度の防衛予算案には、無人機の大規模導入のために1000億円程度の予算枠を想定する計画も盛り込まれています azernews.az+1。
技術比較と戦略的配置の構想
日本政府は、TB2導入検討に加えてイスラエル製のHeron‑2ドローンとの並行評価も進めています。Heron‑2は長時間滞空、高高度での監視に特化した「MALE/UAV」で、TB2は沿岸監視や軽攻撃用途に適した、より操作・展開が容易な戦術級ドローンと位置付けられています Defence Security Asia。
民間報道では、これらを戦略的に組み合わせる「多層型ドローン網」の構想も紹介されており、Heron‑2が広域監視の“目”として、TB2が沿岸や島しょ部の“防衛ライン”を担う構成案が示されています armyrecognition.com+1。
世論の反応と懸念点
SNSや一部識者の間では、次のような意見が交錯しています:
-
性能と実戦性の評価:「TB2は軽量かつ即応能力が高い。導入する価値はある」とする肯定的な声、
-
法整備と独自防衛への懸念:「攻撃型の無人機は専守防衛の枠組みを超えるのでは」といった安全保障上の慎重論、
-
技術依存リスク:「海外頼みの統合装備では、将来的な整備や技術自立が難しくなる」という批判的な視点もあります。
今後の課題と展望
-
導入決定プロセスの透明化と法的支柱の強化
TB2を含むドローンが準備決定される際には、武器使用に関する憲法解釈や議会での説明責任が重要となります。 -
技術移転と国産化の道筋の確保
トルコからの導入が進んでも、将来的に国産あるいは共同開発型の無人機の育成体制を構築することが不可欠です。 -
国際協調と安全保障のバランス
米国を中心とする安全保障体系と並行して、トルコとの新たな産業協力をどう位置づけるかが外交面でも注目されます。
私の感想と考え
私は、この動きを単なる「装備導入」以上の意味を持つ戦略的転換の兆しとして注視しています。TB2の導入は、価格と即応力を兼ね備える魅力的な選択肢ですが、それ以上に懸念すべきは「将来の日本の防衛技術の自主性のあり方」です。
中長期的には、国産無人機開発の推進と海外先進技術との連携によるハイブリッド戦略こそが、日本の安全保障を持続可能なものにすると考えます。