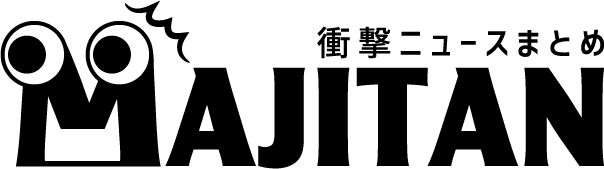佐久本秀行氏急逝、太陽光リサイクル技術の未来に暗雲
佐久本秀行氏急逝、太陽光リサイクル技術の未来に暗雲
概要
岡山県新見市の新見ソーラーカンパニー代表、佐久本秀行氏(49歳)が急逝し、日本の太陽光パネルリサイクル分野に大きな衝撃が走った。氏が中心となり開発してきたCO2排出ゼロの熱分解装置は、日本、中国、インドで特許を取得し、環境負荷の少ないリサイクル技術として注目を集めていた。しかし、政府が使用済みパネルのリサイクル義務化を断念した直後の出来事であり、2030年代に予測される大量廃棄問題への不安はさらに強まっている。社内体制は混乱し、ソーシャルメディアでは陰謀論や政策批判が飛び交い、技術の国際展開の行方が焦点となっている。
背景と経緯
再生可能エネルギー政策の推進により、太陽光パネルの設置は全国各地で急速に拡大した。2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)は、発電事業者にとって大きな参入機会となり、メガソーラーを含めた発電所が各地に建設された。だが、普及と同時に「設置後20~30年で大量の廃棄が発生する」という構造的課題も抱えていた。2030年代後半には50万トン規模のパネル廃棄が見込まれており、既存の処理施設やリサイクル技術では対応が追いつかないと懸念されている。
この状況下で、佐久本氏が率いた新見ソーラーカンパニーは独自の熱分解技術を開発した。この技術は、従来の焼却や埋立処理と異なり、CO2を排出せずにパネルを分解し、ガラスやシリコン、金属を高い純度で回収できる点が革新的とされていた。さらに、日本国内だけでなく、中国やインドといった太陽光発電が急拡大している国でも特許を取得し、国際展開の準備が進んでいた。しかし、政府はリサイクル義務化を見送り、大規模発電事業者への報告義務にとどめる方針を示した。こうした背景での佐久本氏の急逝は、まるで制度的な後退と企業の要となる人物の喪失が重なった象徴的な出来事として受け止められている。
環境的・社会的懸念 / 影響
第一に懸念されるのは、環境汚染である。太陽光パネルには鉛やセレン、カドミウムなどの有害物質が含まれる製品があり、適切に処理されなければ土壌や水系を汚染する危険性がある。大量の廃棄パネルが一度に発生する際、リサイクル施設の能力を超えてしまえば、不法投棄や不適切な埋立が横行する可能性は極めて高い。これにより、農業や漁業への被害、地域住民の健康被害が懸念され、地方社会に深刻な影響を及ぼしかねない。
第二に、資源の損失も問題である。パネルには銀やシリコンといった再利用可能な資源が含まれている。これらを廃棄するだけでは循環型社会の理念に反し、資源確保が困難になる日本にとっては大きな打撃となる。特に国際競争が激しい半導体や電気自動車産業では、資源の再利用は戦略的にも重要だ。
第三に、再生可能エネルギー事業全体への信頼性の低下も挙げられる。これまで「クリーンエネルギー」として推進されてきた太陽光発電が、廃棄段階で「環境リスクを拡大させる産業」と見なされれば、地域住民の反発や協力拒否につながる。すでにメガソーラー建設をめぐっては景観や自然破壊を理由に反対運動が起きているが、廃棄問題が加われば不信感は一層強まるだろう。佐久本氏の技術はこうした不安を和らげる可能性を持っていたが、今後の展開は不透明になっている。
課題とジレンマ
課題は複数あるが、核心は「責任の所在」と「技術の実用化」の二点に集約される。まず、リサイクルの費用を誰が負担するのかという問題が解決されていない。製造メーカーに責任を持たせれば過去に設置されたパネルをどう扱うかが不明確になり、発電事業者に負担を求めれば中小規模の事業者の経営を圧迫する。施工業者に任せるには事業規模が大きすぎ、結果として責任の分散が続いている。
次に、リサイクル技術の普及が進まない点である。佐久本氏の技術は理論的には有望であったが、商業化には莫大な設備投資と制度的後押しが必要だった。政府が義務化を断念したことで、リサイクル事業の市場性は弱まり、結果的に投資が集まりにくくなる。こうした悪循環が続けば、技術革新の芽が摘まれてしまう危険性がある。
また、政策決定の遅れも深刻だ。FIT導入から10年以上が経過しているにもかかわらず、廃棄段階に関する制度設計は整っていない。2030年代の廃棄ピークを目前に控えながら、具体的な責任分担や処理体制を示せていないことは、政治の先見性不足を示すものといえる。
私の感想と考え
私は今回のニュースに深い失望を覚えた。佐久本氏は、日本が抱える再エネ廃棄問題に具体的な解決策を提示し、国際的にも評価される可能性を秘めていた。その人物を失ったことは技術的損失であるだけでなく、日本が環境分野で存在感を示す機会を逸したことを意味する。
政府がリサイクル義務化を見送ったことも、問題の根本を先送りする判断だと私は考える。費用負担の議論が難しいことは理解できるが、だからこそ段階的導入や補助金制度などの緩和策を提示すべきだった。欧州諸国ではすでに製造者責任を明確にし、回収・リサイクルの仕組みを整えている。日本が同様の体制を取れなければ、国際社会における環境政策の信頼性が低下しかねない。
また、SNSで広がっている陰謀論や不信感は、政府の説明不足が生み出した副作用でもある。透明性を欠いた政策決定は、結局国民の不安を煽るだけだ。政治は「説明責任」を果たさなければならない。特に再エネは国民生活に直結するテーマであり、廃棄物処理を含めた長期的なビジョンを示すことが不可欠である。
私は、日本が循環型経済を真に実現するためには、制度と技術を結びつける覚悟が必要だと考える。佐久本氏の残した技術は、その一つの突破口となり得る。氏の急逝を単なる不幸な出来事として終わらせず、次世代の研究者や企業が意思を引き継ぎ、制度面からも支える仕組みを構築することを強く望む。2030年代の廃棄ピークが迫る中、時間的猶予は限られている。いま行動を起こさなければ、未来の世代に深刻な負担を押し付けることになるだろう。
引用元
産経新聞(2025年8月報道)
NHKニュース(2025年8月報道)
環境省公表資料