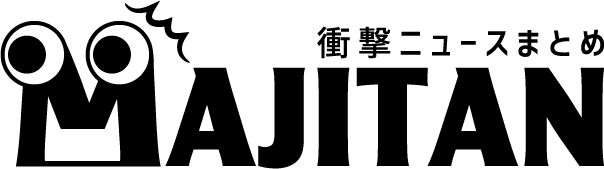地球の自転速度が急上昇、原因は?
地球の自転速度が急上昇、原因は?
概要
2025年7月10日、地球の自転が通常より速くなり、1日が1.38ミリ秒短縮されるという観測結果が報告された。これは、標準的な24時間(=86,400秒)よりもわずかに短い「最速の地球日」の1つとして記録された事象である。
この現象に対して、地球物理学や天文分野の専門家たちは複数の原因仮説を提示しているが、現時点で決定的なメカニズムの特定には至っていない。仮にこの加速傾向が今後も継続または再発する場合、現在の時刻制度に重大な影響を及ぼす可能性があり、「マイナスうるう秒(leap second)」の導入という技術的課題が現実味を帯びつつある。
この問題は、科学的には地球内部・大気・気候変動などが複雑に関係する可能性がある一方、私たちの生活基盤である「時間」の信頼性そのものを揺るがす事態として注視されている。
地球の自転とは何か
地球は約24時間をかけて自転しており、その速度は非常に安定しているように思われがちだが、実際には地質学的・天体力学的な影響を受けて微妙に変動している。たとえば、地震・火山活動・氷河の融解・大気循環などの地球システム全体が影響を及ぼすとされている。
このため、国際的な時間管理機関である「国際地球回転・基準系事業(IERS)」は、地球の自転と原子時計とのズレを常に監視しており、その差異を補正するために「うるう秒(leap second)」が不定期に挿入されてきた。
通常、地球の自転はわずかずつ遅くなっている(減速傾向)が、ここ数年は一時的な加速現象も観測されており、その中でも今回の「1.38ミリ秒短縮」は注目に値する。
自転加速の原因に関する仮説
現時点で考えられている主な原因仮説は以下の通りである:
1. 地球内部の質量移動
地球内部、特にコア(核)やマントルにおける流体的な質量移動が自転速度に影響を与えている可能性がある。たとえば、地球核の回転が地表よりも早かったり遅かったりすることが、全体の角運動量の変動につながる。
2. 氷河融解と地殻反発(グラビティ・リバウンド)
地球温暖化によって大量の氷が融解し、質量が極地から海洋に移動すると、地球の形状や重心バランスがわずかに変化する。これにより地球の回転モーメントが変動し、自転が速まる可能性がある。
3. 大気・海洋循環の変動
エルニーニョ現象や偏西風の変化など、大規模な大気・海洋の質量移動が一時的に地球の自転速度に影響を及ぼすことがある。特に大気上層の風速の変化は、数ミリ秒単位の自転変化に影響しうるとされている。
4. 地震やプレート運動
超大型地震などで地殻が変形すると、地球の回転軸が微小にズレたり、質量分布が変化することで一時的な自転加速が起こるケースも過去にあった。
現時点では、これらの要因が単独で起きているというよりも、複数の微細な現象が重なった結果として、今回の加速が生じたとする見方が有力である。
時刻制度への影響と「マイナスうるう秒」の可能性
標準時(UTC)は原子時計を基準に運用されているが、地球の自転はあくまで「自然現象」であり、両者の間には時間が経つほどずれが生じる。このずれを調整するために、これまで27回のうるう秒が追加されてきた。
しかし、今回のような自転の加速傾向が続けば、初の「マイナスうるう秒」――つまり、1秒を削除する調整が現実に必要となる可能性が出てきた。
これはシステム的にも技術的にも極めて厄介な問題であり、情報システムや金融取引、GPS、通信インフラなど「1秒のズレが命取り」となる分野においては、マイナス調整が想定されていない場合が多く、グローバル規模での混乱も予測されている。
技術・社会基盤への影響
仮にマイナスうるう秒が導入される場合、最も大きな影響を受けるのは次の3領域である:
-
通信・ネットワークインフラ:NTPサーバや分散システムの同期にバグが生じる可能性。
-
金融取引:証券市場や高頻度取引アルゴリズムにおける「1秒の逆転」は、データ整合性や履歴記録に致命的な矛盾を生む。
-
宇宙・天文観測:GPS衛星や天文観測機器では、地球の自転と時刻の一致が前提条件であるため、補正の難度が高い。
そのため、国際電気通信連合(ITU)やIERSを中心に、「うるう秒制度の将来的廃止」も議論されており、「地球の動きに合わせる」か「人為的に固定する」かの選択が問われている。
私の感想と考え
このニュースを聞いてまず驚いたのは、「1.38ミリ秒」というごくわずかな違いが、地球規模の議論や制度設計の見直しにまで発展しているという事実だ。日常生活の中で私たちは「1秒」の重さを意識することは少ない。だが、その1秒がずれるだけで、社会は大きく揺らぐ。
同時に感じたのは、**地球という存在の“生きている感覚”**である。私たちがあたりまえのように「24時間」と思っているその単位が、実は地球の内部構造や気候、果ては人間活動と密接に連動している。この現象は、地球が単なる“静止した天体”ではなく、今も微細に呼吸し、変化し続けている証拠だ。
特に印象的なのは、「マイナスうるう秒」の導入という未体験の領域に踏み込むかもしれないという点だ。加えて、地球物理学・気象学・情報科学・宇宙工学といった分野が、一斉にこの1秒の調整のために連携しなければならない状況は、まさに高度にシステム化された文明社会の脆さと強さの同居を感じさせる。
私たちは、日々の“時間”を疑わずに過ごしている。しかしその時間は、地球の動きという物理的な基盤の上に成立しているにすぎない。そして、もしその基盤がわずかに揺らげば、私たちの世界もまた揺れる。それが今回の報道が教えてくれる最大の教訓だ。
地球のわずかな変化が、技術にも制度にも、そして我々の感覚にも影響を与える――この事実を前にすると、自然の巨大な力に対する敬意と、時間という概念への再認識を強く迫られている気がする。私たちは「時間を支配している」のではなく、「地球に時間を許されている」だけなのかもしれない。
【地球の自転速度が急上昇 に関する引用元↓】
NHKニュース「地球の自転速度が急上昇、原因は?」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250724/k10014451421000.html