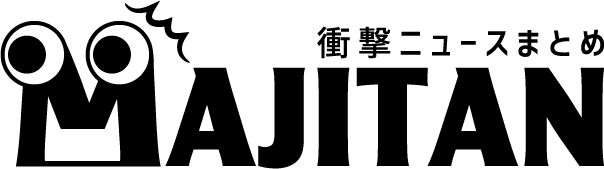7月25日はかき氷の日:夏の暑さと冷たい甘味の話題
7月25日はかき氷の日:夏の暑さと冷たい甘味の話題
概要
7月25日は「かき氷の日」として知られており、夏の風物詩として親しまれるかき氷文化の象徴的記念日である。この記念日は、かき氷の古称「夏氷(なつごおり)」にちなみ、語呂合わせ(なつ=7、ご=5、おり=2+5=7)と、1933年に山形市で日本最高気温40.8℃が記録された日である「最高気温記念日」とが重なることから制定された。
この日には全国各地でかき氷に関するイベントやSNS投稿が活発になり、様々な味や創作スタイルのかき氷が楽しまれている。また、イラスト投稿・ファンアート・VTuberによる配信コンテンツなどでも、「かき氷」をテーマとした表現が多数登場しており、単なる食べ物を超えた夏の象徴的モチーフとしての存在感が際立っている。
「かき氷の日」の由来と気象の歴史
「かき氷の日」は、記念日としての由来が明確である。まず第一に、「かき氷=夏氷(なつごおり)」という古語に由来し、7(な)月25(つごおり)日という語呂合わせが成立すること。さらに1933年7月25日に山形市で観測された**日本国内最高気温40.8℃**の記録にちなみ、「最高気温記念日」としても位置付けられている。
この記録は長年破られず、気象庁においても「日本の気象史に残る日」とされており、夏の厳しさを象徴する意味合いを持っている。そうした意味で、「かき氷の日」は単なる“スイーツの日”ではなく、猛暑と向き合い、涼を求める人間の知恵と文化の記念日でもある。
かき氷の進化と地域性
かき氷は、日本において古くから親しまれてきた夏の甘味であり、その起源は平安時代にまで遡るとされている。『枕草子』にも記述が見られるなど、長い歴史を持つ和の涼味だが、近年ではそのスタイルと技術が大きく進化している。
現在では、以下のようなバリエーションが広く展開されている:
-
純氷使用の専門店型かき氷:透明で硬度の高い純氷を薄く削り、ふわふわした食感を実現
-
シロップの多様化:昔ながらのイチゴ・メロンに加え、抹茶、黒蜜きなこ、チーズフォーム、季節の果物を使った贅沢系
-
トッピング文化の拡張:練乳・餡・果肉・グラノーラ・ゼリーなど、和洋折衷の複合デザートへと進化
-
地域限定メニュー:宇治金時(京都)、日光天然氷(栃木)、沖縄ぜんざいなど、地域文化と融合した独自系
また、屋台・カフェ・観光地のみならず、近年では冷凍技術の進化により、コンビニスイーツや家庭用冷凍食品としても高品質なかき氷が登場している。
SNS文化・デジタル空間での展開
2020年代以降、かき氷は単なる“食べるスイーツ”にとどまらず、ビジュアルコンテンツとしても強い存在感を示している。SNS上では以下のような動きが顕著だ:
-
Instagram・X(旧Twitter):フォトジェニックなかき氷写真が数多く投稿され、季節の風物詩として可視化
-
VTuber・配信者コンテンツ:かき氷をテーマにしたASMR動画、夏季限定の衣装や背景演出として使用
-
ファンアート・イラスト投稿:各キャラクターがかき氷を食べる様子、擬人化された“氷精”などの創作が拡散
-
3Dモデリング・メタバース:バーチャルイベント空間内で“かき氷屋台”を再現する取り組みも進む
これにより、かき氷はリアルとバーチャルの両面で、夏を象徴するコミュニケーションツール・文化表現として機能している。
夏の生活文化としての位置づけ
かき氷は「清涼感のある嗜好品」であると同時に、暑さへの適応戦略の一つでもある。特に日本の夏は湿度が高く、体温調節の難易度が高いため、冷たい食物を通じての内側からの熱対策は重要な意味を持つ。
実際に、かき氷の冷却効果は以下の点で注目されている:
-
口腔内を冷やすことで脳温が間接的に下がり、暑さによる集中力低下を緩和
-
甘味によって血糖値が一時的に安定し、熱疲労によるイライラの抑制
-
水分摂取を兼ねることで、脱水予防の補助的手段にもなる
ただし、冷たすぎるものを急激に摂取すると、胃腸への負担や「アイスクリーム頭痛(brain freeze)」の原因になるため、適量・適時の摂取が推奨されている。
私の感想と考え
このニュースを目にして、単なる「スイーツの日」を超えた文化と気候の交差点としての「かき氷の日」の意義を改めて考えさせられた。かき氷は、ただ美味しいから食べるのではなく、「暑さをどう乗り切るか」という知恵と感性が詰まった料理だと言える。
特に印象深いのは、その“普遍性”と“可変性”の両立である。屋台で100円で食べる懐かしい味から、高級料亭で提供される芸術的な一皿、そしてコンビニで買える実用的な冷菓に至るまで、かき氷は常に“今”に適応し、誰にでも開かれた存在であり続けている。
また、VTuberやSNS投稿を通じて、かき氷が“ビジュアルの清涼感”として共有されていることにも興味を惹かれる。実際に食べなくても、「かき氷の写真を見るだけで涼しく感じる」体験は、デジタル時代の“感覚共振”の一例だと感じた。これはもはや味覚だけでなく、視覚や共感性にも作用するマルチセンサリーな存在と言えるだろう。
一方で、かき氷が“猛暑の象徴”であるという現実にも直面する。今年の夏も全国で体温を超える猛暑日が続いており、かき氷を食べることが「贅沢」ではなく「生存戦略」になりつつあるとすら感じる。そう考えると、かき氷は単なる季節の風物詩ではなく、日本人の気候適応文化の中核にある存在かもしれない。
最後に、私はこの“かき氷の日”という文化的記念日が、未来の日本においても、気候・技術・表現が融合した形で受け継がれていくべき日だと強く思う。猛暑と闘う私たちにとって、かき氷は美味しさとともに、「涼しさをデザインする知恵」そのものなのだ。
【7月25日はかき氷の日 に関する引用元↓】
NHKニュース「7月25日はかき氷の日:夏の暑さと冷たい甘味の話題」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250724/k10014451711000.html