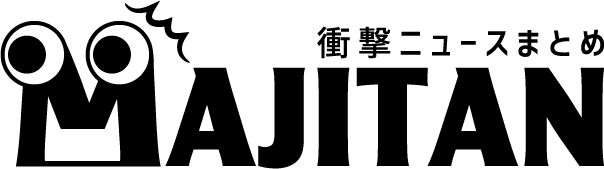税理士試験簿記論で難問発生
税理士試験簿記論で難問発生
概要
2025年8月5日、全国の会場にて令和7年度(2025年度)税理士試験の簿記論科目が実施された。
今年度の試験では、例年通り理論・計算の総合力を問う3問構成が出題されたが、特に第3問の難度が高く、多くの受験生が時間配分に苦しんだとの声が相次いでいる。
一方で、第1問・第2問は比較的オーソドックスな内容となっており、「部分点を確実に取れた」という反応も見られた。
出題構成と難易度分析
2025年度の簿記論は、以下のような出題構成で実施された(受験生の報告・予備校速報ベース):
-
第1問(仕訳問題):会計処理の基本を問う小問集合。
→ 頻出パターン中心で「標準レベル」 -
第2問(個別計算):連結会計とリース取引の混合問題。
→ 一部ひねりがあったが、過去問演習者には対応可能との評価 -
第3問(総合問題):複雑な貸倒引当金・棚卸資産評価・法人税等調整を含む統合問題。
→ 時間配分・計算過程ともに「難易度が非常に高い」との声多数
とくに第3問については、「設問が多岐にわたる」「一部資料が分かりづらい」「途中で見直し時間がなくなった」など、処理スピードと判断力の両立が問われる内容となっていた。
受験生の反応とSNSでの声
試験直後のX(旧Twitter)上には、以下のような投稿が目立った:
「第3問、手応えなかった…詰んだ」
「第1・2問で稼げたけど、3問目でメンタル崩壊した」
「第3問の資料が鬼。1ページ目でつまづいた」
「毎年変化球来るけど、今回は割とストレートな出題だった気がする」
また、試験後に実施された某予備校の速報アンケートでは、全体の難易度について「昨年よりやや易しい」と評価する声が5割を超えている一方、「第3問の破壊力が強すぎた」として全体的には“標準~やや難”との判断が多かった。
試験制度と年度による傾向の変化
税理士試験は、計算能力の精度とスピード、そして複数論点を統合する力が求められる高度な国家試験であり、毎年一定の傾向変化が見られる。
特に簿記論では、以下のような変化が進行中:
-
基礎問題と応用問題の二極化傾向
-
計算過程の正確さ>答案の最終数値重視へのシフト
-
新収益認識基準、リース基準変更など会計制度改正の影響反映
-
時間内完走の困難化(問題文の長文化、資料の複雑化)
このため、「試験技術」としての時間配分・設問選択・部分点狙いの戦略が年々重要となっている。
私の感想と考え
私は今回の簿記論をめぐる反応を通じて、現代の税理士試験が単なる知識試験を超え、業務対応力を問うプロフェッショナル試験に進化していると強く感じた。
特に第3問のような統合問題は、単純な解法暗記では太刀打ちできず、「資料を読み取り、本質を見極め、必要情報を構造化する力」が不可欠だったように思う。
また、試験制度全体としても、「満点よりも部分点」「丁寧に処理した痕跡を残す」という価値観が定着しつつある。
これは実務に通じる姿勢でもあり、私は非常に健全な方向性だと評価している。
一方で、出題側が難問を投入する場合には、「受験生がどの論点にどれだけ時間をかけるべきか」という戦略の余地をきちんと残す設計が重要だ。
難しさだけが先行し、思考時間も得点機会も奪われる構成では、真に優秀な受験生を見抜くことはできない。
今後は、計算処理能力とともに、時間配分・設問選別・取捨選択の訓練がますます求められるだろう。
私は、今回の試験を機に、受験界全体で「技術的対応力」の育成が一段と進むことを期待している。
【引用元】
-
全国税理士受験予備校「2025年度 簿記論科目 解答速報・分析」
https://www.zeirishi-school.jp/bokiron/2025-analysis.html -
SNS(X)投稿ハッシュタグ #簿記論2025 #税理士試験
https://x.com/search?q=%23簿記論2025&src=trend -
国税庁「税理士試験について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiken/zeirishi/index.htm